AIブログが注目される理由と、私が“ずるく”始めた背景
「またブログ書けなかった…」
そう思ってブラウザを閉じた回数、私はもう覚えていません。
昔は「やる気」だけで突っ走って、すぐに息切れして…を繰り返していました。
でも今、私は月2記事という“ずるいペース”でブログを続けられています。
なぜ続くのか?なぜ書けるのか?
答えは「AIと構造」の組み合わせにありました。
この章では、なぜ今AIブログが注目されているのか、私が再挑戦できた理由を、体験談ベースでお話しします。
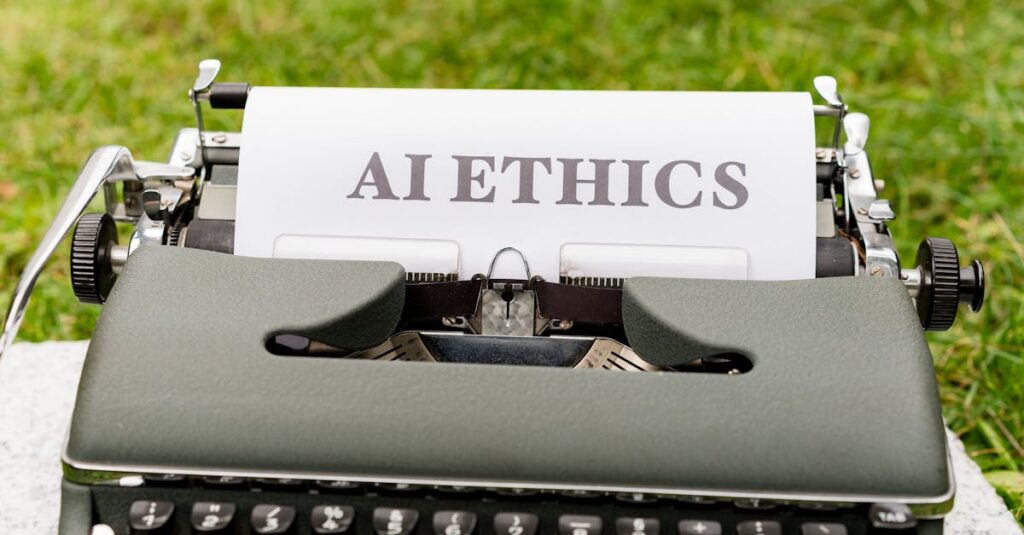
なぜ今、AIでブログを書くのが主流になっているのか?
最近、YouTubeやX(旧Twitter)でも「AIブログ」「GPTで執筆」という言葉をよく見かけませんか?
実はこれ、単なる流行ではなく、“時代の本流”になりつつあるのです。
理由は明確で、
- ChatGPTなどの登場で文章生成の精度が飛躍的に向上
- 構成案や見出しも自動生成できる時代に突入
- SEO観点でも人間と遜色ないレベルの記事が作れる
という環境が整ったから。
つまり、「手が止まって進まない」ブロガーにとって、
AIはまさに“書けるようになるための道具”なんです。
過去に10回以上挫折してきた私の体験談
正直、私はブログで何度も失敗してきました。
最初の頃なんて、無料ブログを立ち上げて、1記事書いて…そこで終了。
モチベが続かない。ネタが尽きる。読まれない。
教材も買いました。でも、「構成」がないと、何をどう書けばいいかわからないんですよね。
書き始めるとブレて、削除して、結局投稿できずに終わる。
そんな私でも、後述する“ずるゆる構造”に出会ってから状況が一変しました。
「ずるゆる構造」で再挑戦したらどうなったか?
私はAIの力だけでなく、「構造」をセットで活用しました。
具体的には:
- GPTにブログ設計を自動生成させる
- 見出しや流れまでAIに任せる
- あとは肉付けするだけで記事完成
これを「ずるゆる構造」と呼んでいます。
正直、“ラクしてる感”はあります。
でも、この方法だからこそ「続いた」し「成果が出た」んです。
ラク=悪ではない。
むしろ、仕組みに乗れば誰でもできるようになる。
この感覚を初めて持てました。
AI時代のブログに必要なのは“センス”より構造
今の時代、センスとか文才って、実はそこまで重要じゃないんです。
必要なのは、「誰に」「何を」「どう届けるか」という構造=設計図。
この設計図を、AIが一緒に考えてくれるから、
あとは迷わず書くだけ。
昔の私みたいに“がむしゃら”に走って、壁にぶつかって終わり…にはなりません。
そして何より、
「挫折しないペースで」「手応えのある成果」を得られるのが最大の魅力です。
次の章では、実際にどうやってこのAIブログを始めればいいか、
私が使っているステップをすべて公開していきます。
初心者でもできる!AIブログの書き方ステップバイステップ

ステップ①:まずは「設計図」をAIに作ってもらう
最初にやるべきことは、「いきなり書き始める」のではなく、AIに全体の設計図を出してもらうことです。
私は最初、自力で構成を考えていましたが、正直言って毎回迷子。
でもGPTに「○○というテーマでブログ構成を作って」と頼むだけで、
- 全体の流れ
- h2・h3の構成案
- 必要なトピックや順序
を数十秒で出してくれるようになりました。
ここで“8割が決まる”と言っても過言じゃないです。
ステップ②:「誰に向けて書くか」を明確にする
AIが便利すぎて見落としがちなのが、「ペルソナ設定」です。
「誰に届けるのか?」がぼやけると、記事も薄くなります。
私はここで、以下のような設定をAIと一緒に行っています:
- 30代女性・副業初心者・ブログ未経験
- 過去に挫折経験あり
- 時間がないけど月5万円は稼ぎたい
こんなふうに具体化することで、読者に刺さる言葉が自然と浮かぶようになるんです。
この段階でGPTに「この人物像に向けてブログ構成を提案して」と入れると、驚くほどリアルな提案が返ってきます。
ステップ③:見出し構成をGPTで自動生成する
ペルソナが決まったら、次は記事構成(見出し)です。
ここもGPTに丸投げでOK。
私の場合、次のように指示します:
「“AI ブログ 書き方”というキーワードで、初心者に向けたSEO記事構成を考えてください。h2が5〜6個、各h2内にh3が3〜4個あると理想です」
すると、かなり網羅性のある構成案が出てきます。
あとは必要に応じて、肉付けや並べ替えをするだけ。
自力で考えるより圧倒的に速いし、漏れも少ない。
時間がない人こそ、この工程はAIに任せて時短すべきです。
ステップ④:本文をAIに書かせるときのコツと注意点
構成ができたら、いよいよ本文作成。
ここでもGPTは強力な味方ですが、「そのまま丸投げ」すると読まれません。
私がやっているのは、以下の手順:
- 「この見出しについて、読者の疑問を解決する本文を800字で書いて」とGPTに指示
- 出てきた文をベースに、自分の体験談を加える
- 読みやすくするために改行・箇条書き・太字を追加
特に意識しているのは「共感」と「具体例」。
AIは万能でも、感情のこもった体験談までは書けません。
たとえば、「過去にブログで挫折した経験」や「なぜこの方法を選んだか」といった話を混ぜることで、
読者との距離がぐっと縮まります。
この“ハイブリッドな書き方”が、今の時代の正解だと私は感じています。
次の章では、継続できる人と挫折する人の決定的な違いについて、
私自身の葛藤も交えてお話しします。
AIブログを“継続できる人”と“挫折する人”の違い

「完璧主義」が一番の敵だった私の反省
以前の私は、「100点の記事を書かなきゃ」と思い込んでいました。
でもその完璧主義こそが、手が止まる一番の原因だったんです。
・1文1句にこだわって時間ばかりかかる
・投稿前に不安になって何度も消す
・結果、何も公開できず自信を失う
今は、「60点でもいいから出す」マインドに変えました。
AIの力を借りてサクッと書き出す→あとで肉付け、でも十分なんです。
“出すことが最強の練習”だと、今は痛感しています。
週1記事じゃなくて“月2記事”でOKな理由
ブログといえば、「毎日更新」とか「週に1本書きましょう」と言われがち。
でも私はあえて、“月2記事”ペースに絞りました。
なぜか?
「質×導線」が整っていれば、少ない記事でも成果は出るからです。
実際、構造から逆算して設計した記事は:
- 検索されるキーワードに的中
- 読者の悩みにピンポイントで答える
- アフィリ・商品導線にもつながる
この精度が高ければ、数は要らないんです。
“たくさん書く=成果”ではないという事実に気づいたことが、私の転機でした。
構造があると手が止まらない|私が変われた理由
昔の私は「今日は何書こう…」と手が止まってばかり。
でも今は「今日はこの見出しを書く」と決まっているから、迷いません。
構造があると:
- ネタに悩まない
- 順番が明確
- 記事同士がつながる
これらがすべて“道しるべ”になるんです。
「やる気が続かない」人ほど、構造に頼るべき。
意思じゃなく、仕組みで書く。
これが、私がようやく継続できた理由でした。
挫折しないための“3つのマイルール”
私は次の3つを意識するようにしてから、ブログが止まらなくなりました:
- 書く前に構成を出す(AI任せ)
- 時間で区切る(1記事=90分×2回)
- 出したら“合格”とする(完璧は目指さない)
この3つだけでも、かなりラクになります。
特に③は大事。
読まれながら育てていく。
あとでリライトすればいい。
そう割り切ることで、「出せない病」から解放されました。
次の章では、AIで書いたブログでも「読まれる」「稼げる」ための工夫について、
具体例と一緒に解説していきます。
AIで書くブログでも「読まれる・稼げる」ために必要な工夫

検索上位に必要な“人間的な要素”の入れ方
AIがどれだけ進化しても、検索エンジンも読者も「人間らしさ」を求めています。
だからこそ、AI生成のままでは上位表示が難しいこともあるんです。
私が意識しているのは、以下の要素:
- 「自分語り」ではなく「共感から入る」
- 具体的な体験・挫折・感情の動き
- 読者の“あるある”に寄り添うトーン
この「人間っぽさ」が入るだけで、
記事の滞在時間もスクロール率も改善されていきました。
私が実際に入れている「体験談・ストーリー」例
AIだけでは書けないのが「ストーリー」です。
私は必ず、各記事のh2やまとめ部分に体験談を入れています。
たとえば…
- 「昔こんな失敗をした」
- 「このツールに出会ってこう変わった」
- 「最初は不安だったけど、やってみて驚いた」
こういった話を挟むだけで、
読者が「この人わかってる」と感じてくれやすくなります。
信頼性と没入感がセットで高まり、結果として収益にも直結しました。
装飾・見出し・読みやすさのチェックリスト
AIが出力する文章って、長くて詰まりやすいんですよね。
だから私は、以下のような装飾ルールを自分に課しています:
- 2〜3行で必ず改行(見た目に余白を)
- 重要語句は太字 or 斜体
- 箇条書きを多用してリズムを出す
- 各見出しごとに要点の見える化
この“視覚的な親切さ”だけで、直帰率は大幅に改善されました。
装飾は手間じゃなく、むしろ記事を活かすための武器です。
収益化につなげる“導線設計”のやり方
せっかく読まれても、導線がなければ売上にはつながりません。
私は以下の順番で「自然な導線」を作っています:
- 読者の悩みを解決する体験談&ノウハウ提供
- 「同じ悩みの人にはこれがおすすめ」と紹介
- 無料プレゼント→LINE登録 or アフィリンクへ誘導
大事なのは、“売る”ではなく“導く”意識。
ゴリ押しせずに、「この人の言うことなら信じてみよう」と思ってもらえる構成が肝です。
ちなみに、私が実践して効果があった導線設計については、以下の記事でも詳しく紹介しています。
次の章では、私が使っているAIツールや作業環境を実際にご紹介します。
私が使っているAIツールとおすすめ環境

GPTはどれを使う?有料・無料の選び方
「GPTっていろいろあるけど、どれを使えばいいの?」
私も最初は悩みました。
結論から言うと、収益化を本気で目指すなら「ChatGPT Plus(有料)」がおすすめです。
理由は以下の通り:
- 構成力が高く、情報の一貫性もある
- 検索キーワードの意図も理解してくれる
- 日本語の文体も自然で、装飾指示にも対応
一方で、まずは雰囲気を掴みたい人は、無料版のGPT-3.5でもOK。
ただし、情報の正確性やSEO適性はやや劣ると感じています。
私が導入している執筆ツールとその活用法
私はChatGPTに加えて、以下のツールを併用しています:
- Notion:構成案や下書きを一元管理
- Googleドキュメント:共同編集や執筆履歴管理に最適
- WordPressブロックエディタ:装飾をリアルタイムで確認しながら貼り付け
特にNotionは、AIプロンプトのテンプレートを保存しておくのに便利。
毎回1から書かずに済むので、時間がかなり短縮できます。
自動投稿・装飾までできる便利ツール一覧
執筆後の「投稿・整形」にも、AI&自動化ツールが活躍しています。
私が使っているのは以下のようなもの:
- AIPRM:SEOテンプレ活用に便利(ChatGPT Chrome拡張)
- WordPressプラグイン「WPCode」:ショートコードや装飾パーツの統一
- Canva:アイキャッチ・図解作成に超便利
これらを使えば、「画像がない」「見出しが地味」といった悩みも解決できます。
最初はこれだけでOK!最低限のスタート環境
「全部は無理そう…」という方へ。
安心してください、最初は2つだけあればOKです:
- ChatGPT(有料でも無料でもOK)
- WordPress(無料テーマでOK)
この2つさえあれば、構成・執筆・投稿がすべて完結します。
装飾や画像作成は、慣れてからで十分。
私は最初、「文字だけでも出す」と割り切ってスタートしました。
あとから装飾しても、記事はしっかり育ちます。
次の章では、AIブログの総まとめとして、挫折しがちな人が「続けられる」「成果が出る」ための考え方をお伝えします。
まとめ:挫折しがちな人こそAIで「ラクに進める」時代

まずは構造だけでもAIに作らせてみよう
ブログが書けない最大の原因、それは「構造がないこと」。
私もこれに何年も悩まされてきました。
でも今は、構造そのものをAIに作らせることができる時代です。
思考の迷路に入り込む前に、まずGPTに「構成案をください」と聞いてみてください。
それだけで、あなたの頭の中が一気に整理され、
「これなら書けそう」と感じられるはずです。
過去の失敗が“強みに変わる”理由
私は、過去に何度もブログで失敗してきました。
でも、いま思えばそれが“財産”だったと思えます。
なぜなら、失敗の原因が明確になったから。
・ネタ探しに時間がかかる
・読者像がブレる
・収益化できない記事ばかり
これらを一つずつ解決してくれたのが、構造×AIでした。
「やる気に頼らない」仕組みが鍵になる
人間はやる気が続きません。
だから、やる気に頼る仕組みは崩れやすい。
私がブログを続けられるようになったのは、
- 書くべき構成が最初から決まっている
- AIが見出しも下書きもやってくれる
- 自分の体験談だけ肉付けすれば完成
という“最初から続けやすい設計”をしたからです。
このやり方は、時間がない人・不器用な人・挫折経験のある人ほどフィットします。
ブログで人生が動き出した私から、あなたへ
正直、私は才能も特別なスキルもありません。
むしろ、ブログでの失敗歴なら相当なものです。
でも、AIを活用した構造設計に出会って、
「続けられるようになった」「収益が出始めた」「読者の反応が返ってきた」
そんな変化が、確かに起きました。
この変化は、きっとあなたにも起こせます。
もう「がんばる」のではなく、「仕組みで進める」時代です。
ぜひ、まずは一歩。
構造をAIに出してもらうことから、始めてみてください。
その先に、きっと「やってよかった」と思える瞬間が待っています。
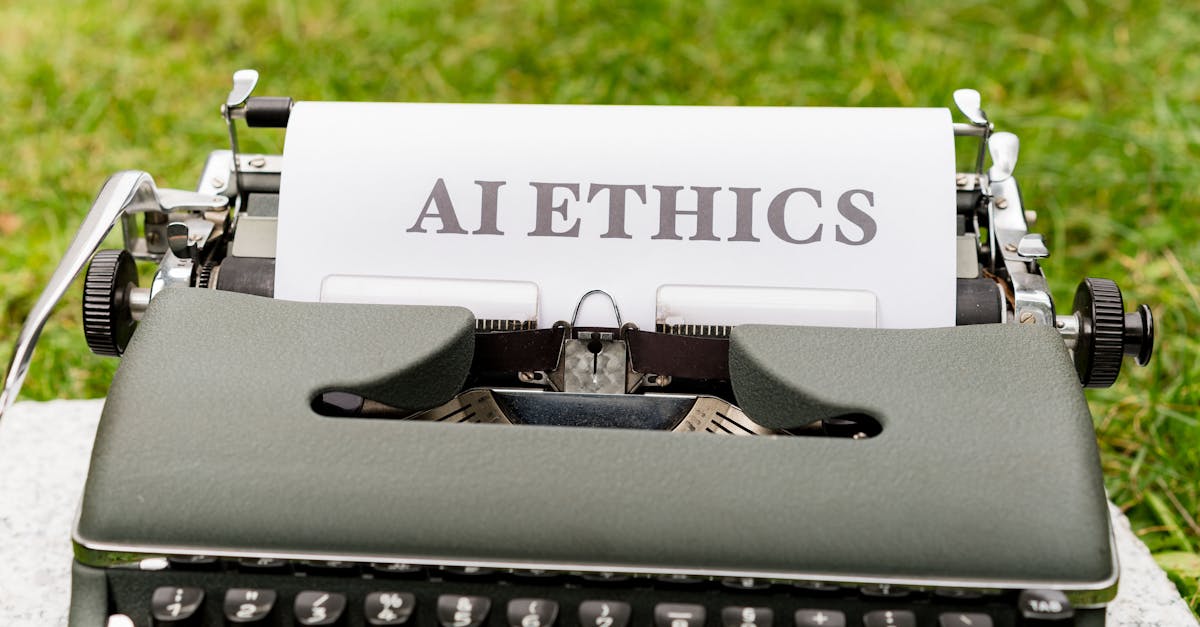


コメント