「また今日も、ブログのネタが思いつかない…」
これは、私が毎日のように感じていた悩みでした。
ネタ帳を眺めてもピンと来ない。
キーワード選定ツールを開いても、何を書けばいいか定まらない。
正直、何度も「今日はもうやめとこう…」とブラウザを閉じた日があります。
そんな私が、AIを活用し始めてからは一変しました。
今では、10分で20個以上のネタ案をAIに出してもらい、その中から“刺さる記事”を選ぶという効率的なスタイルに。
この記事では、私が試行錯誤の中で見つけた
「AIを使ったブログネタの量産法」を、具体例とともにご紹介していきます。
AIを使い始めてネタ探しの悩みが一掃された話
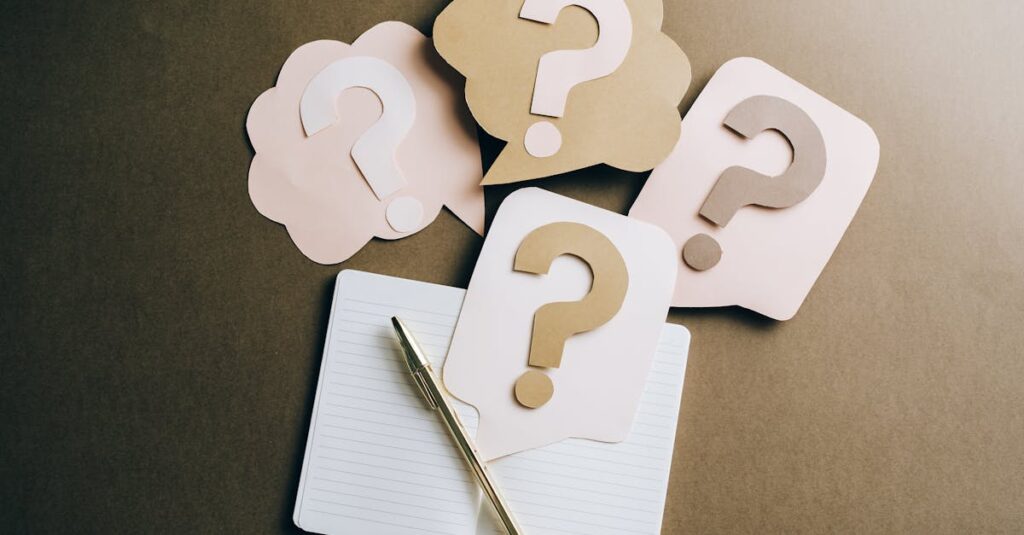
昔の私は「今日何書こう…」が日課だった
ブログ歴3年になる私ですが、
初期の頃はとにかく「ネタがない」が口グセでした。
毎朝パソコンの前で10分、20分と唸る日々…。
どれだけツールを見ても、自分の中からアイデアが湧いてこなかったんです。
キーワード選定もしていましたが、
選んだキーワードを見ても「で、何を書くの?」という状態。
ネタ=記事の切り口が見えていなかったんですね。
ChatGPTに出会ってからの変化とは?
そんな中、話題になっていたChatGPTを試してみたのが転機でした。
半信半疑で「◯◯ジャンルでブログ記事のネタを10個ください」と入力すると…
想像以上に的確で、しかも「これは面白い」と思える切り口ばかり!
今までの悩みは何だったんだ…と衝撃を受けました。
しかも、思考のきっかけにもなるんです。
「このネタは、この読者層なら刺さるかも」
「これをステップ記事にすれば、導線になるな」と
AIに任せることへの抵抗とその克服
最初は「こんなのに頼っていいのか?」というモヤモヤもありました。
でも今は違います。
「ネタを出すのはAI、精査と構成を考えるのは自分」
この役割分担で、むしろ自分の頭も整理されるようになったんです。
感覚的には、
「ブレスト相手が24時間いてくれる感じ」
1人で悩まずに済むことで、記事作成もグッと前に進むようになりました。
実際に成果が出た記事の裏側を公開
実際にこの方法で出したネタから生まれた記事がこちらです。
「副業初心者が月1万円稼ぐためのジャンル選定3ステップ」
このネタは、ChatGPTに「副業ジャンルに悩む初心者向けの記事ネタを10個」と聞いた中の一つ。
そこから構成を組み、実体験と合わせて書いたところ、検索順位3位&月300アクセスを安定獲得できています。
自力で考えていたら、たぶん出てこなかった切り口でした。
AIのアイデアが「自分では気づけない視点」を提供してくれる。
それが最大のメリットだと今は感じています。
AIでブログネタを生み出す基本ステップ
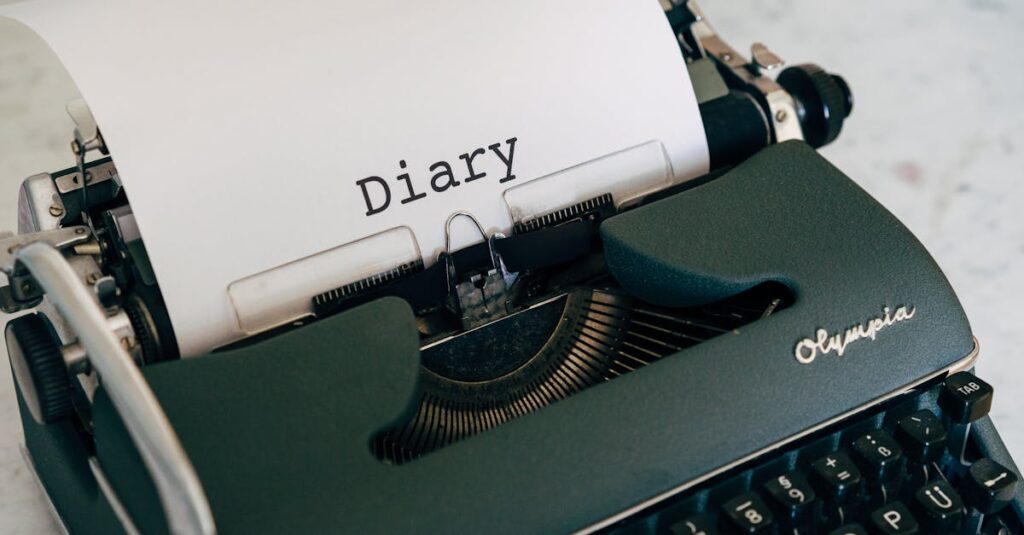
最も簡単:ChatGPTに「ネタ出しお願い」と聞くだけ
正直、最初はこれだけでも十分です。
たとえば、私がよく使う定番プロンプトはこちら:
「副業初心者向けに役立つブログ記事のネタを10個ください」
これを打つだけで、ジャンルに合った切り口がズラッと出てきます。
AIは情報の整理が得意なので、
「自分で考えると似たようなアイデアばかりになる…」
という悩みも解消されました。
プロンプトの工夫で精度が劇的に変わる
ChatGPTに慣れてくると、“聞き方”のコツが見えてきます。
たとえば、こんなふうに条件を付けると精度が上がります:
- 「検索ボリュームがありそうなキーワードを含めて」
- 「共感されやすいストーリー構成を意識して」
- 「読者の悩みが強いテーマに絞って」
実際、プロンプトを変えるだけでAIの出すアイデアが別物になることも珍しくありません。
私は今、毎回必ず「この読者層に向けて」「こんな切り口で」と明確に条件を指定して出すようにしています。
ネタの方向性に迷ったら「ジャンル×悩み」で突破
「何をテーマにすればいいか分からない…」
そんな時は「ジャンル」×「読者の悩み」という軸で考えるのが鉄則です。
たとえば私の場合:
- ジャンル:副業ブログ
- 悩み:ネタ切れ、収益が出ない、時間がない
この組み合わせでChatGPTに
「副業ブログを始めた人が“ネタ切れ”に悩んだ時に響く記事ネタを5つください」
と聞けば、共感性の高い内容が出てきやすくなります。
私が実際に使っているテンプレートも公開
ここで、私が日常的に使っているネタ出し用のプロンプトテンプレートを紹介します:
「◯◯ジャンルで、ターゲットは△△な人。
この人に刺さるブログ記事のネタを10個、できれば検索意図も添えてください」
このテンプレで、以下のような出力がされます:
- 記事タイトル案
- 想定する読者
- 検索意図
- 記事構成の概要(h2案)
これらを元に、自分なりの要素を足して肉付けすれば、
「書くべきことが最初から整っている」状態がすぐに作れます。
ネタ出しに時間を取られていた頃と比べて、執筆にかけられる時間と集中力が倍増しました。
おすすめAIツールと使い分け戦略

無料で使える代表ツール3選
私が初期に使っていたのは、以下の3つの無料ツールです。
- ChatGPT(無料版):日常のネタ出し・プロンプト練習に最適
- Notion AI:下書きや要点整理が得意
- Google Gemini(旧Bard):最新のトピックに強い
特にChatGPTは、無料でも十分に使える機能が揃っているため、まずはここから始めるのがおすすめです。
有料ツールの価値とコスパ比較
有料版を使うと、出力の質・速度・精度が段違いです。
私はChatGPT Plus(月20ドル)を契約していますが、「1記事で元が取れる」と実感しています。
さらに、記事構成まで自動化できるツールも増えていて、たとえば:
- SEOライティング特化のAI(例:SurferAI)
- 日本語対応の国産AI(例:Catchy、ミライAI)
どれも数千円〜の月額ですが、時間単価の改善を考えれば十分回収可能です。
日常の思いつきをAIで整理する裏技
「ふと浮かんだアイデア」が埋もれてしまうのはもったいない。
私はiPhoneのメモアプリに思いついたキーワードを入れておき、
あとでChatGPTに「このキーワードで記事の切り口を5つください」と依頼しています。
これだけで、“なんとなく”が“具体的なネタ”に昇華されるんです。
「迷ったらこれだけでOK」なツール紹介
結論として、最初の1本はChatGPT(Plus推奨)で十分です。
補助的に使える無料ツールとして:
- Ubersuggest:検索ボリュームの参考に
- Googleトレンド:今の話題を掴む
これらをChatGPTと組み合わせることで、
質も量も満たされたネタ出し環境が整います。
私はこれだけで月10本ペースの記事ネタをストックし、
その中から週1〜2本を厳選して書くスタイルを続けています。
AIネタ出しを「継続できる仕組み」にする方法
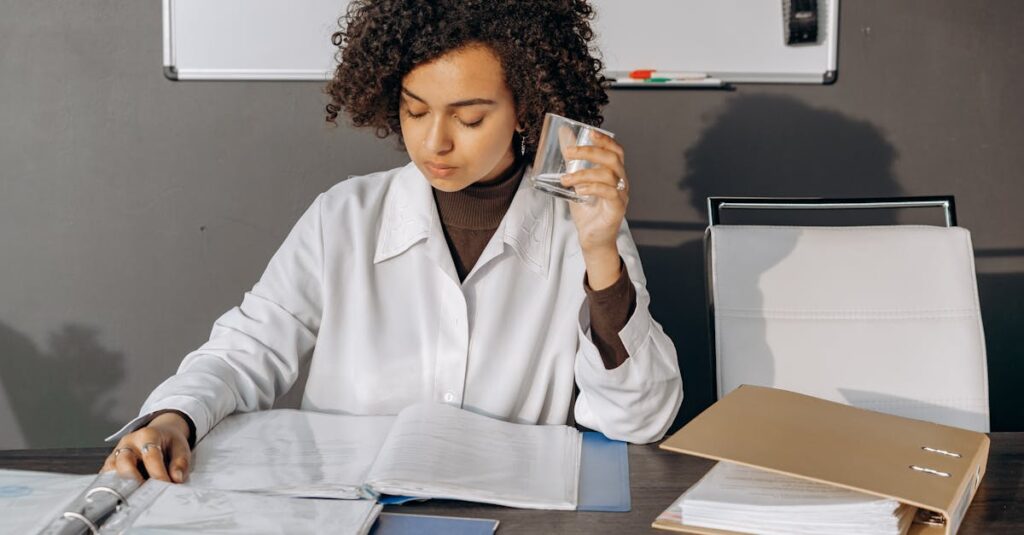
ネタ帳アプリ×AIでストック管理
ブログは「書く前の準備」で8割が決まる。
これは私が身をもって実感していることです。
そこで役立っているのが、ネタ帳アプリとAIの組み合わせ。
私の使い方はこんな感じです:
- 思いついたワードや悩みをメモアプリに保存
- 時間があるときにChatGPTで「構成案」や「タイトル案」に昇華
これを週1の習慣にするだけで、いつでもネタが出せる状態を保てます。
「毎週ネタ出しDAY」で無理なく続く
ブログは継続が命。
だから私は、毎週月曜朝を「ネタ出しDAY」に固定しています。
やることは簡単:
- メモアプリから気になるワードをピックアップ
- ChatGPTに構成案を依頼
- Googleスプレッドシートに記録(ネタ管理台帳)
こうすることで、ネタ出しに悩む時間がゼロになり、
「書くだけ」に集中できるようになりました。
ChatGPTを“編集者”として使うと強い
AIはただの「アイデア出し役」ではなく、“編集者”としても超優秀です。
私は構成ができた段階で、こんなプロンプトを活用します:
「この構成を元に、h2ごとに読者の検索意図に沿った見出しをh3で4つずつ出してください」
さらに、「この見出しで1000字ずつ本文を作って」と追加すると、
1記事丸ごとの草案が完成します。
そこに私の体験談や独自の視点を加えることで、
唯一無二の“Mr.Sブログ”が仕上がるんです。
モチベ維持に役立った3つの仕掛け
正直、ブログが続かなかった理由の9割は「しんどさ」でした。
でも今は、次の3つでモチベを保てています:
- 1)ネタ出しはAI任せ → 書くハードルが下がる
- 2)成果が見える仕組み → スプレッドシートでPV/収益記録
- 3)仲間と報告し合う → X(旧Twitter)で週報ツイート
特に「AI任せでいい」と思えたことが大きく、
精神的な負担がかなり軽くなりました。
結果、月2記事ペースでも継続できるようになり、
アクセス・収益ともに右肩上がりになっています。
AI任せで大丈夫?不安を払拭するヒント

「内容が薄い」と感じるときの対処法
AIで記事を作ると、「なんか浅いな…」と感じる瞬間があります。
それは、体験談や主観が不足しているからです。
AIは客観情報の整理は得意でも、人間の経験や感情までは書けません。
だからこそ、「私の場合は〜」という一言を加えるだけで、ぐっと深みが出るんです。
読者ニーズとAIアウトプットのギャップを埋める
AIが出す記事は、基本的に「一般論寄り」です。
でも実際の読者が求めているのは、「自分の悩みにピンポイントで刺さる答え」。
そこで私が意識しているのは、以下の流れです:
- 検索キーワードで「どんな悩み」があるかリサーチ
- AIに「この悩みを持つ人に向けた記事」を書かせる
- 読者の立場になって添削・加筆
AIをたたき台にして、共感される文章に仕上げることで、反応率が大きく変わります。
信頼性を高める“体験談の差し込み方”
Googleもユーザーも、今は「信頼できる情報」を求めています。
私は必ず、各セクションの冒頭か末尾に「自分の失敗談・成功談」を入れるようにしています。
たとえばこのように:
実はこのパートの内容、私も最初は全然できていませんでした。
書くたびに「これでいいのか?」と不安になって手が止まっていたんです…
こうすることで、読者との距離感がグッと縮まります。
自分の言葉とAIの融合で最強に
結論として、AIだけでもダメ、人間だけでもしんどい。
だから私は、AIを“型”と“下地”にして、自分の視点で仕上げるスタイルに落ち着きました。
このスタイルにしてから、
- ネタ出し→執筆→投稿が最短2時間で完了
- 読者からのコメントやシェアが増加
- 自分自身も「また書きたい」と思える
AI=作業効率化、人間=感情と信頼の担保
この役割分担で、AIブログ運営は“怖くない”ものになります。
まとめ:AIと一緒に、ブログを「続けられる趣味」に

今回ご紹介したように、AIを活用することで
「ブログのネタが思いつかない」「何を書けばいいか分からない」
という悩みは一気に解消されます。
しかもAIは、疲れない・待たせない・毎回全力で応えてくれる頼れる相棒です。
私自身、AIと組むようになってから:
- ネタ探しにかかる時間が1/5に
- 構成に迷う時間がほぼゼロに
- 「また書きたい」と自然に思えるように
何より、「続けられる趣味」になったことが一番の収穫でした。
ブログは副業としても、表現の場としても、人生を豊かにしてくれるものです。
そこにAIという味方が加わることで、努力に頼らず“継続できる”仕組みが完成します。
もしあなたが今、ネタ出しや執筆に悩んでいるなら…
まずはChatGPTに「ブログネタ出して」と話しかけてみてください。
その一歩が、新しいブログライフの扉を開くかもしれません。
それでは、また次の記事でお会いしましょう。
Mr.Sより


コメント